否定されたキリスト
現代カトリック教会が抱える諸問題の起源
ポール・A・ウィッケンス 著
『フマネ・ヴィテ』研究会 成相明人 訳
原著 Christ Denied
Origin of the Present Day Problems in the Catholic Church
著者 Rev. Paul A. Wickens
訳者からの一言 — 筆者ウィッケンス神父は超保守主義者として知られています。例えば「教会の外に救いなし」ということは真理ではありますが、彼が支持するフィーニー神父はこれを文字通りに解釈して、1949年4月18日ボストン教区長クッシング枢機卿から聖職停止、同年8月8日バチカンからも注意を受け、1953年には破門されています。皮肉なことにフィーニー神父の墓標には「教会の外に救いなし」と刻まれてあります。訳者はウィッケンス神父の超保守主義に同調するわけではありません。だれが書いたかでなく、何が書かれてあるかに注目した上で皆さんに本論を紹介します。大筋としては日本の教会にとって非常に大事な文献です。 成相明人
導入
「一致」と「共同体」は進歩主義者たちにお気に入りの言葉です。神の計画によればわたしたち人間は言葉の意味を大事にする理性を備えているわけですから、それが一体どのような「一致」と「共同体」であるか考えてみることが必要でしょう。何しろ、泥棒とか俗世的ヒューマニストも、「一致」とか「共同体」とか言われる仲間意識で結ばれていることがしばしばあるわけですから。
ところが、キリストと一致するはずの共同体、教会との一致の中に、三位一体、実体変化のようなある種の教義を大事にせず、また教皇の首位権を余計な重荷と見なす傾向が見られるのはどういうことでしょう? そういうことがあれば、キリストと教会を中心にする共同体はもう存在していません。ペトロのいるところに教会がある、という格言を作った初代キリスト教徒はそれをよく理解していました。
御父である神の下に、この世におけるイエス・キリストの代理者が享有する権威下にあるローマ・カトリック教会だけが、救いにつながる唯一そして本物の共同体です。
この一致からわたしたちを引き離す者は、聖書が警告する偽りの共同体を作ろうとする偽りの教師であり、わたしたちは勇気を出してこのようなたくらみを告発しなければなりません。
偽りの共同体を作り、カトリック教会に分裂をもたらす計画の首謀者が悪魔自身であることは疑いもない事実です。堕落した天使であり、高度の知性を備える悪魔はイエス・キリストの教会を打ち負かそうとして、高度に組織化された終わることない計画の首謀者です。多くの人間が、悪魔の道具、時としては意識的代行者、または無意識的協力者になります。個人にどれほどの責任があるかは最終的に神だけがご存じです。
永遠の真理を否定し、真理をゆがめ、信者を混乱させた二十世紀のこのような運動で目立つのは二人の人物です。平均的信徒、その限りでは平均的司祭とか修道者も、タイヤール・ド・シャルダンとカール・ラーナーについてそれほど深くは知りません。普通、二人の名前は時々新鮮なカトリック知識人として、いわゆる進歩主義者たちが口にします。しかし、実際に彼らの著作を研究し、彼らの思想を分析した人たちがどれほどいるかというと、これは大きな疑問であると言わねばなりません。この小冊子のねらいは、主にタイヤール・ド・シャルダン、カール・ラーナー両神父と、現今のカトリシズムに彼らが及ぼした影響を平均的読者に伝えることです。
神の恩寵を願いつつ、この責務を果たすに当たって著者は神である主の模範に倣うよう努力しました。福音を読むと、優しく、穏やかな方として描かれる主は、反対派をやりこめるために時として強い言葉で非難なさいますし、乱暴な行為もなさいます。「偽善者であるあなたたち」とか「まむしの子孫」なども救い主である主の口から出た言葉です。
旧約時代の数多い預言者に倣って、聖イェロニモも、強く、きつい言葉をためらいなく選択したものです。ある時などは信仰を捨てた異端者について説教壇から「あのサソリが死んでしまった今…」とまで言ったものです。
魂に対する愛徳のために、イエス・キリストの優しさと強さを適切に取り入れることを希望しつつ、著者は読者諸氏に、わたしたちの信仰に何が起きたか、そして現代、神学校や小教区で吹き荒れているこのひどい異端の発端の責任が、だれにあるかを歯に衣着せず伝えるつもりです。
ポール・A・ウィッケンス
その取り次ぎを祈りつつ神の御母に本書を捧げます。
1981年8月15日 被昇天の祝日
否定されたキリスト
一章 現代カトリック教会が抱える諸問題の起源
カルヴァリオに向かうイエスを見て涙したエルサレムの婦人たちのように、傷ついた教会を見て心あるカトリック信徒も泣き悲しみたくなります。
復活祭の朝、空になった墓を見たマグダラのマリアはおろおろして「だれかが主を墓から取り去りました。どこへ置いたのかわかりません」と言いましたが、1980年代の教会も正にそういう状態にあります。
ここ15年間に起こった教会内の破壊的変化はどのように、またどこから生じたのでしょうか? それはすべて実に急激に起きました。初めは不愉快という程度であったかもしれませんが、すぐにそれらの有害な変革の数々は、神秘体の生命に思いも寄らぬ衰微をもたらしました。なぜでしょうか? 荘厳な儀式が行われる教会に大勢の信者が集まり、修道院とか神学校が満員だったのはつい最近のことのように思われます。規律、道徳、キリストを通じての聖化、御聖体を皆当時は大事にしていたものです。
現代神学の間違った諸傾向になぜこれ程の勢いがついたのだろうか、どのようにしてこれらの傾向が教会生活のすべてのレベルに浸透してしまったのであろうか、と人は不思議に思います。
これらの傾向は究極的に道徳的堕落と客観的倫理規範の無視をもたらしました。これはすべて神法に反し、真正カトリシズムが明らかに衰微した原因になっています。救い主イエス・キリストが教えた真理はまるでドミノ倒しのように倒されています。
教会という城塞が攻撃されているのに、アメリカとヨーロッパの教会指導者たちは状態を改善する努力を怠っているかのように見えます。
神の助けを得て、本論で著者は、信仰喪失と道徳低下の原因が知的そして霊的には、人祖アダムとエバの現実と、さらに三位一体の人格神の拒絶にあることを証明するつもりです。これらの不信の種は、ピエール・タイヤール・ド・シャルダンと呼ばれる男の著作に含まれています。
ジョージ・タイレルとタイヤール・ド・シャルダン
1901年の夏、フランスでは神学生が神学校から法律によって強制的に退去させられ、国外で神学研究を続けることになりました。反聖職者主義的フランス政府が修道会を敵視する法律の立法化に成功したからです。しかし、最終的分析によれば、迫害者であった政府より修道会の方が教会の健康にとってはもっと危険でした。
ともかく、迫害の主な目標はイエズス会でしたから、彼らは全員国外に退去するよう求められました。行く先は当然ドーバー海峡の向こう側にある英国でした。フランス人神学生の中に混じっていたのが、司祭職を目指していた若いタイヤール・ド・シャルダンでした。
そういうわけで、ド・シャルダンと同級生たちはジャージーにあったイエズス会修道院に引っ越すことになりました。英国でこれらの若いイエズス会員たちはジョージ・タイレルという名前のアイルランド人イエズス会員に大きな影響を受けることになったのです。その影響は非常に強力なもので、当時英国にはただ一人だけイエズス会員がいて、その名前はジョージ・タイレルであったと言っても誇張でないほどです。
最近タイレルに興味を持ち始めた著者は、カトリック教会における現在の困難を引き起こす原因になったとして非難したい過去のすべての人たちの代わりに、タイレルだけに全責任を負わせたくなるほどです。
近代主義者タイレルの影響
当時、つまり今世紀の始めごろ、恐るべき異端が諸神学校に広がりつつありました。自他共に認める主導者がイエズス会のジョージ・タイレル神父でした。彼は引っ張りだこで、非常にしばしばオックスフォード大学でも講座を受け持っており、そのほかの大学でも影響力の大きい教職に就いていました。イエズス会の月刊誌編集にもかかわり、自ら百近くの論文を寄稿しています。内容は飽きることもなく霊性と内的生活に関する自分の思い込みというものでした。そこまでは許せるとしても、彼には一つ大きな問題がありました。おそらく彼は神を信じていませんでした。自分が描いた神の戯画なら信じていたいたかもしれませせん。しかし、「人が内的にも外的にも礼拝することを義務づけられる啓示された三位一体の神、至高の存在、自由意志と知性を備えた独立した存在」である神を信じていたとは言えません。キリストが処女から生まれたこと、キリストが復活したことを彼が信じていなかったことに間違いはありません。
ほとんどの異端と同じく、彼も自分の思いつきを満足させるような霊性を発展させ、機会あるごとに飽きることなくそれを推奨したものです。そのための黙想会指導とか研修会で各地に旅行したり、雑誌に寄稿したり、著書を出版したりしていました。このような努力の目的はもちろん新開発の霊性の推進、つまり非常にキリスト教的であるためにはどうすればいいかの伝授でした。表面的に見ると、真理と誤謬が巧妙な言葉遣いで混合された彼の運動は、カトリック信者をキリストへの新鮮でさらに純粋な愛に招いているようにも見えたものです。しかし、タイレル自身と彼に近かった人たちにとって、カトリシズムの基盤は神話でしかありませんでした。もちろん彼にしてみれば、暴露されたこのような神話は当然放棄されるべきでした。
★彼のアメリカ版とでも言える進歩主義者リチャード・P・マックブライエン神父は、最近、二巻からなる「カトリシズム」(ウィンストンプレス、29ドル95セント)を発行していますが、彼は書中でタイレルを弁護し、1907年彼を異端として譴責した教皇ピオ十世を非難しています。それだけではなく、彼はタイレルをこともあろうに十字架の聖ヨハネ、聖ペトロ・カニジウス、聖ロベルト・ベラルミヌスと同列に取り扱っています。
歴史的事実に徹すれば、カトリック・エンサイクロペディアにはタイレル神父が最終的には、イエズス会の長上から自分の異端的記事を公に撤回するよう求められたことが記載されています。タイレルがそれを拒否したので、彼は聖職停止の処分を受けた挙げ句イエズス会から退会処分を受けました。
その後、彼は自分を受け容れる司教を探しましたが、成功しませんでした。それでも彼は正統信仰に反する記事を書き続けたのです。教皇ピオ十世による近代主義の断罪(1907年)を激しく非難し続けたために、彼は名指しで破門され、その赦免は聖座に留保されることになりました。
その後何年かたって彼はブライト氏病で死にましたが、最後まで悔い改めることがなかったために教会墓地への埋葬を拒否されています。
二章 そのほかにもあった初期の影響
一世紀から、教会には懐疑主義の小さなグループが常に存在していました。堕落した本性、生活のおごり、肉欲は絶えずすべての人に影響を及ぼします。信徒であってもその影響から免除されるわけではありません。
時代を下がると、この懐疑思想は十八世紀のドイツで盛んになり、★後に国境を越えてフランスにも広がりました。十九世紀末までにそれはフランスでも広く受け容れられるようになり、そこでの主な指導者はイエズス会のアンリ・ブレモン神父でした。上述のジョージ・タイレル神父はブレモンの親友であり、その結果、その近代主義的・進歩主義的原理に大きく影響されることになります。
★ルーテル教徒であったエンマヌエル・カントは、1700年代に多かった懐疑主義者の典型です。彼の理論は間違った前提に基づいていました。それらの前提の一つは人間の知識が確かなものではあり得ないということでした。次に、彼らは(いわゆる)真理が常に変化すると考えるました。最後に、理性的霊魂の部品である理性と自由意志よりも本能と情欲を重んじるべきであると主張したのです。
ここで著者が論じたいのは、タイレルを堕落させた著名な懐疑主義者アンリ・ブレモンは、タイヤール・ド・シャルダンが学んだ高等学校、コレージュ・ド・モングルで教えていたという事実です。当時14歳だったド・シャルダンはここでブレモンに教わり、その影響を受けています。ですから読者は彼が若年時からとんでもない誤謬思想にさらされていたことを理解できるでしょう。
わき道になりますが、ド・シャルダンが1955年に死亡したとき、教会の断罪を受けていた彼の著作は非合法的に印刷・出版され、広く頒布されたものです。出版者はタイヤールがその「独創的で革命的」思想を、第一次世界大戦中つまり彼が中国に滞在していた期間に発展させたような印象を与えるよう細心の注意を払ったものです。しかしこれはナンセンスでしかありません。実際のところ、ド・シャルダンの思想に新しいものは何一つありません。彼の思想は高校時代と英国で神学校に入っていた時代に習ったことの受け売りです。彼が主張する異端思想は、彼の少年時代にすでに流行しており、その発端は更に時代をさかのぼります。
著者の主張を証明するために言いますが、1893年とド・シャルダンが神学校に入った1899年の間に、教皇は基本的真理と聖書自体に関する懐疑主義を断罪する四つの回勅を発することを余儀なくされました。1907年7月3日、聖座はあの有名な教令『ラメンタビリ』を発表しました。1907年9月8日、教皇ピオ十世はその回勅『パッシェンディ』で近代主義★がもたらす害毒に関してカトリック世界に警告を発しました。
★近代主義の簡単な定義を知っておくと便利です。それはまず、カトリックの宗教、信仰、道徳が現代化されなければならないと主張します。そして、啓示されたすべての教義は疑ってかかります。つまり懐疑主義です。そして多くの教義を結局は否定してしまいます。近代主義がもたらすのは恩寵の喪失であり、そこから懐疑はますますつのり、それがさらに恩寵を失わせる結果になります。
この運動の中心はイエズス会のアンリ・ブレモン神父であり、その弟子が同じくイエズス会のジョージ・タイレル神父で、同会のタイヤール・ド・シャルダン神父がさらにその衣鉢を継いでいるのです。タイレルと同じくブレモンも自分の近代主義を広めるに当たっては決して疲れを知りませんでした。フランスの(いわゆる)知識層はその種の会合があると必ずと言っていいほどブレモンを講師として招いたものです。ですから彼はほとんどいつでも「列車に乗って」、ヨーロッパ中の懐疑主義者たちに講演するために旅行していました。1899年、アンリ・ブレモンはフランスのイエズス会誌エチュードの編集者に任命されました。この任命はまるで大地震のようなものでした。正統カトリック信者であればその影響が極めて重大であると感じたものです。エチュード誌提供の公の発表の場を得て、ブレモンの哲学はすぐにイエズス会全体に及ぶことになりました。
しかし、ブレモンにとっては残念なことでしたが、彼の近代主義標榜は多くの人々の反発を買い、彼はイエズス会から退会することを求められます。最終的に彼は教区の司祭になりましたが、残念なことにその精神はいろいろな意味で同会に残ってしまいました。
ブレモンのエチュード編集を引き継いだのは、レオンス・ド・グランメゾンというイエズス会員でしたが、彼はもっと賢く、用心深い性格の人でした。しかし、その神学は前任者のそれと全く同じでした。彼は用心深くローマとの対決を避け、その哲学と神学の誤謬をいかにももっともらしく覆い隠していました。彼こそ自分はカトリックであると言いながら基本的教義のどの部分でも選択的に信じる(例えばカール・ラーナー、ハンス・キュング、エイヴリー・ダレス、リチャード・マックブライエン神父などのような)現代自由主義者の原型であったと言えるかもしれません。
ジョージ・タイレルと同じく、ド・グランメゾンも英国イエズス会神学校で教えていました。実に、必須科目を履修したタイヤール・ド・シャルダンやその他多感な年代にあった神学生たちは近代主義神学の二連発を食らったようなものでした。
タイヤール・ド・シャルダンの履歴
ド・シャルダンは神学生時代に多くの書簡を書いていますが、司祭生活の初期、文章を書くことが自分の好みにあっていることを発見します。ド・グランメゾンが編集人を降りたころから、彼はエチュードに記事を送り始めます。その後三十数年の間、彼は自分の思想を同誌で発表し続けました。正統信仰を守る番犬である教会権威者たちに神学的逸脱を指摘されないよう、彼はその内容をあいまいにするためにある程度の注意を怠りませんでした。合計すると彼の著作はかなりの量になり、1930年代半ばまでに彼は近代主義を広める本業では有力な指導者になっていました。
タイヤールの戦略・中国訪問
有名になる前のド・シャルダンは、残念なことに十分な聴衆を自分自身もしくは自分の思想に引きつけるだけの魅力に欠けていました。人々の注目を得るための行動を思い巡らしていた彼がそこで思いついたのが中国訪問です。タイヤールはもし自分が中国にしばらくの間滞在して、何か異国情緒のあることでもすれば、自分が高名な旅行家としての名声を得ることになると考えたものです。そうすれば、人々は彼を尊敬し、彼の主張にもっと耳を傾けることになり、彼のメッセージも伝わりやすくなろうというものです。
彼にとって不運であったのは、彼がフランスに帰国した時点までに、特に原罪の教義を攻撃する彼の論文のいくつかがヴァチカンの検閲官に送られていたことでした。イエズス会の長上たちはある程度の知的寛容を見せてくれてはいましたが、ローマは烈火のように腹を立てており、この男については直ちに何らかの処分をするように求めていました。それで、彼の困惑と恐怖にもかかわらず、長上たちは彼を中国に再任命してしまいました。これがタイヤールの気に入るわけがありません。引き続いてではないもののその後二十年もの間彼は中国に滞在することになりますが、中国語を学ぼうとはしませんでした。彼は中国にはもう飽き飽きしていたのです。中国人と彼らの生き方は嫌いでした。どうしてこんなことが分かるのかといえば、彼が書いた数多くの書簡があるからです。そう言えば、彼の書簡は長くて、支離滅裂な彼の本よりはるかに分かりやすいのです。
さて、彼はその著書で「ヌー圏」のような新しい言葉とか、「人間化」「メタキリスト教」「心理的惑星化」「オメガ点」とかそのほかにも多くの短命な言い方を発明しました。それらは正に文字通りに彼が勝手に作り出した言い方にしか過ぎず、ことさらに何も意味はありません。この点、フランス語は便利です。フランス人は表現と言葉の明瞭さに誇りを持っています。ですから、ド・シャルダンがこれらの言葉を発明したのは、自分の思想をあいまいにするためでしかありませんでした。
(例えば原罪に関する)彼の著書とか記事で彼が成し遂げたのは、以前ジョージ・タイレルが広めたあの奇異な霊性を普及することでしかありませんでした。
三章 誤謬の点検
不可解なことに、最近英国と米国では、タイレルの著書が再評価され、賞賛さえされています。タイレルを読んで感じるのは、今日のカール・ラーナー、かつてのタイヤール・ド・シャルダンとの酷似です。考え方はいつでも同じです。
誤謬のカタログ
A 教義に対する不忠実
近代主義者は、カトリックのほぼすべての教義に対して忠実であることを丹念に避けるような宗教用語を使用します。
彼らは少なくとも公にはカトリックの教義を真っ向から否定することはまれです。その代わりの戦術は以下のようなものです。
1 例えば教皇の不可謬権、無原罪の御宿り、原罪などのような教義には、あたかもそれらが存在しないかのように決して触れようとしません。
2 または、例えば「霊」という本物のカトリック用語を使用しますが、それを例えば「御父と御子から発出する三位一体の第三のペルソナである聖霊」のように明瞭に定義しないよう気を付けます。
このテクニックの他の例を挙げると、近代主義者たちが洗礼と御聖体についてどのように語るかを見ればいいのです。彼らはこれらの秘跡に特有な二次的効果について長々と教えます。そうすることによって、彼らは含蓄的に(信仰箇条でもある)第一義的効果を否定してしまいます。洗礼は「原罪による死からの復活」ではなく「入門の式」になります。ミサは聖なるいけにえではなく、「食事」とか「アガペ」になってしまいます。★
★普通「感謝の祭儀」もしくは「典礼」が「ミサ聖祭」の代わりに使用されるようになります。この感謝の祭儀が聖なる食事である聖餐、主の臨在、御体と御血、主イエス・キリストの魂と神性と同一視されることはありません。
B 目に見える宗教的しるしの廃止
彼らの基本的思想は以下のものであるように思われます。キリストはわたしたちの中におられる、★つまり、キリストはわたしたちの外には存在しないので、教導職はキリストを代理することがない、などの考えが繰り返して提示されるのです。
★「キリストはこの世に生まれるすべての人を照らす真の光」であるのですから、ここに幾分かの真実があることは否定できません。聖ヨハネは確かにそう言っていますが、ほかにも多くのことを言っていることを見落としてはなりません。聖ヨハネにはペトロと弟子たちの上に聖霊が降ったこと、キリストは可視的秘跡、可視的教義、そして特に可視的統治権を伴う真の意味で社会である可視的教会を創立したことへの信仰がありました。
ジョージ・タイレルは教会を直接には攻撃しません。しかし、彼は(彼の言葉に従えば)目に見える宗教的しるしがいかに大事でないかについて多くのページを割いています。目に見える宗教的しるしは彼に言わせるとカトリックらしいものであればほとんどすべてを含みます。ロザリオは目に見える宗教的しるしの一部です。御像とかメダイユ、聖水、聖体拝領台などはすべて目に見える宗教的しるしに属します。司教たちとかヴァチカンとかそのほかの類似したすべてのものも目に見える宗教的しるしです。人間の奥深くにあるものを除いて、外にあるものはすべて目に見える宗教的しるしであり、タイレルは人々にこれらのものを極力捨て去ることを勧めたものです。★
★現代流行の神学を調べると、現在見られるカトリック的習慣の衰微の底には正にこのような思想が潜んでいることに気付きます。この言葉自体の意味はあいまいではありますが、キリストとの「出会い」はいつでも「わたしの体験」であって、教導職に対する内的そして外的な従順を意味するものではありません。
C 神と人との混同
ド・シャルダンはわたしたち人間を神的環境の一部と理解します。これはもう汎神論に限りなく近い考え方です。ここではタイヤールが、自分と合流するであろうと考えていたある棄教者に宛てた手紙を引用しましょう。「わたしはあなたがおっしゃる反汎神論的立場を取っているわけではありません。わたしは思考法においても気質的にもその反対に本質的に汎神論者です」。
シャルダン主義の主張者であるカール・ラーナーは、わたしたちが皆「無名のキリスト者」であると考えます。(十九世紀初期から教会内に留まる懐疑主義者たちは「カトリック信者」よりも「キリスト信者」という語を好みました。歴史はここでも繰り返されています)。ラーナーの言う無名のキリスト者とは、一体だれのことでしょうか? 人々は自分が知らなくとも、自分がそれを望まなくても、自分にはそんなことに関心がなくてもキリスト信者である、と彼は言うのです。「あなたはいやおうなしにキリスト信者であるのです」。カール・ラーナーが世界にもたらしたメッセージはこんなものです。すぐに気付くのはラーナーの霊性がタイレルのそれと酷似しているということです。
それに増して進んでいるのは、ド・シャルダンが主張する「宇宙が実体変化させられている」とするあのあほらしい思想です。
★1980年代以降の正統カトリック信者は、なぜ近代主義に染まったカトリック信者が御聖体を礼拝しないのだろうか、とかなぜ聖体降福式とか四十時間の聖時間に興味がないのだろうか不思議に思うものです。答えは彼らの考えによると、キリストは御聖体におられるのと同じ意味でどこにでもおられるからです。ある進歩的スポークスマンは「お互いの中にあるキリストの臨在だけが唯一の大事な臨在である」と、いみじくも言っています。
このような思想が神学校でもう長いこと教えられています。1960年にこのような考えがいわばデビューを果たしたわけですが、少し歴史を調べると、これは決して新しいものではないことに気付きます。
四章 増大するド・シャルダンの影響
数多く残されているド・シャルダンの手紙を読むと、1935年までは自分の思想がイエズス会フランス管区で評判がいいことを喜んでいるのが分かります。
ヒットラーが台頭したヨーロッパの人たちが不可避に見えた戦争の気配に息を潜めていたころ、ド・シャルダンはドイツの勝利を推測していました。シャルダン主義によれば「力は正義」であり、彼はヒットラー総統が手にする権力を熱狂的に支持していました。彼はフランス人が退屈で、未開であるだけでなく、反動であるとさえ思っていました。それに比べて、ヒットラーには動的で現代的な神秘主義があり、これ以上のものは望めませんでした。
しかし、ヒットラーに関してド・シャルダンにもある程度の警戒感はありました。それで、占領後の安全を確保するために彼は国外脱出を試みます。行く先は中国で、第二次世界大戦終了までそこに留まるのですが、今回は多かれ少なかれ自分の希望によるものでした。
転換点
この困難な時期のどのイエズス会総長も、フランス管区会員たちの無分別行為を監督しようと試みてはいます。しかし、そのような努力がなされたのも、当時の進歩的傾向に弱腰であったベルギー人ヤンセンス神父がイエズス会総長に選出されるまでのことでした。
それだけにとどまらず、そのころイエズス会の月刊誌エチュード編集長になったのがド・シャルダン思想の熱烈な支持者ルネ・ドゥアンス神父でした。タイヤールは同誌編集人の地位を得て、以前はささやき声で広めようとしていた説を今度は屋根の上から大声で述べることができるようになりました。タイヤールは友人に手紙で「二十年前にわたしをフランスから追い出した理由になったことを、今度は公に広めるためにこの地位が与えられたのは明らかです」と書き送りました。
さて、このようにしてド・シャルダンは戦後復興の途にあった生まれ故郷フランスに帰国することになりました。そのころ、カトリック学究たちをめちゃめちゃにしていた異端も盛んになりつつありました。
警戒するローマ
進む非キリスト教化
タイヤールを迎えることになったパリ大司教の反応は複雑でした。何しろ大司教区はすでにいろいろと問題を抱え込んでいたからです。当時広く読まれた1948年のあの有名な書簡「成長か?衰微か?」で、大慌てのスアール大司教はパリが大騒動になったことを認めています。当時、おろかしい思想がいろいろ出回っていました。カトリシズムの「開かれた窓」に興奮しまくるのが大流行でした。大司教は心配げに「よく分かりませんが、いいこともあるでしょう」などと書いておられます。大司教は知識層が「いつも自分が正統カトリックであるかどうか心配してばかりいるあの恐怖症から解放」される必要を以下のような文で強調したものです★。
★スアール枢機卿の文章を直接引用します。「知的作業は独立しているべきです。教会には技術的問題を直接解決する使命はありません。教会はそれぞれの権威筋が持つ合法的自律性を認めています」。
1960年代初期から中期にかけて、ヨハネ二十三世が召集した第二バチカン公会議中、タイレル、ド・シャルダン、ラーナーの理論は公会議の左翼陣営つまりフランス、ベルギー、ドイツ、カナダ、米国中西部の司教たちの口を通じて語られることになります。同じ論法はすでに1948年、スアール枢機卿の手紙に見受けられます(エンマニュエル・スアール枢機卿著作集、Fides Publishers、シカゴ、1953年参照)。
正統信仰の声
しかし、薄い膜の向こうにある近代主義的傾向を見抜いて、三十年間も注意深く警戒していた一人のドミニコ会司祭がいました。その名はレジナルド・ガリグー・ラグランジュ。
彼らが以前に増して堂々と誤謬の宣伝を始めたとき、ラグランジュ神父も動き始め、教皇ピオ十二世に彼らを破門するよう強く勧告しました。しかし、教皇が断固とした処置を取るべきであり、それを見届けるまでは片時も猶予できない、と彼が確信したのは、1948年、あのつまずき多い手紙でパリのスアール枢機卿がこれらの動きを多かれ少なかれ祝福したときでした。
このような事情で、教皇ピオ十二世はその意義深い回勅「フマニ・ジェネリス」(1950年)を出されることになりました。全カトリック世界に向けられたこの回勅で「ある人たちは不賢明に、また軽率にも進化がすべての生物の起源を説明すると主張し、世界が間断なく進化しているなどという一元論的そして汎神論的意見を恐れもなく支持している」と言われたとき、教皇の念頭にあったのはタイヤール・ド・シャルダンでした。
司祭になった進歩主義者たちは関連するあらゆる学問の分野に進出して、既成の価値を転覆しようとしていました。そのためにこれらの進歩主義者たちがもたらした損害を説明し尽くすことは困難です。なぜこのような戦略について分かるかと言えば、著者の手元には1916年にタイヤールが書いた「工場」建設を提案する手紙があるからです。彼の提唱する「知的工場」、現代で言えばシンクタンクでは、あらゆる分野から進歩的思想を持つ人間が集まって協力することを希望していました。そうすれば種々の分野で進歩的思想はカトリック信者を解放することができるというものでした。倫理神学、教義神学、教会法、聖書研究、その他がこれらの分野には含まれます。彼のリストには自然科学も含まれるのですが、その部門での指導者はタイヤール・ド・シャルダン自身に他なりません。
五章 ド・シャルダンは科学者? 人類学者?
もしある科学者がとてつもなく意義深い発見をすれば、彼が有名になることは保証されます。タイヤール・ド・シャルダンはこのことを百も承知していました。それで、彼は自分の経歴に一つのみならず二つの大発見ではくを付けることにしました。その一がいわゆるピルトダウン人、そして後には信じられないような幸運もあってペキン原人(シナントロプス・ペキネンシス)までも発見することになります。
人類学者であればだれでもピルトダウン人が間違いなく神話、つまりインチキそして意図的詐欺であることを承知しています。タイヤールは大英博物館の二人の高級職員と共謀して意識的そして意図的に信じられないような作り話をねつ造しました。特に、タイヤールの誠実さを信じる人たちはピルトダウン人の話を聞けば、落胆そして当惑させられます。
ピルトダウン人発見の序章
1881年生まれのピエール・タイヤール・ド・シャルダンは、幼少時から化石とか古代の岩石に興味を示していました。そういうものは彼を夢中にさせたものです。彼がイエズス会修練院に入っていたころ、一時的に教師としてエジプトに派遣されたことがありました。1905年から1908年にかけて、彼はイスマイリアで物理と化学を教えていました。エジプト滞在中に彼はファユーム地方にある有名な化石地層で一個の化石を発見し、それは当時彼の名前で呼ばれていたものです。哲学研究生であった1908年以前のことですが、彼はジャージー島で地学調査も行っています。
彼の崇拝者の一人などは彼のことを「科学の遊牧者」と呼んでいますが、彼の経歴を見ればうなずけるように、それは彼が若年時に始まり死去に至るまでしばしば旅路にあったことを示唆しています。
真理の軽視
タイヤールは司祭叙階直後、理由は不明ですが、ピルトダウンに近い英国ヘイスティングスにある小さな家での滞在を許可されました。そこで彼は著者が知る限り特に何をするでもなく時を過ごしました。もっとも彼の書簡によると彼は深く黙想していたそうではあります。彼がその小さな家に到着するやいなやおびただしい数の「偽造された」化石が登場して、それらは地球の年齢が十万年であることを証明すると言われ始めました。これらの化石の中にあの悪名高いチンパンジーのあごの骨が混じっていました。それは確かに人間の頭蓋骨に似ていないこともありませんでした。ド・シャルダンはこれこそがホモ・サピエンスの祖先に属したことに疑いないと宣言したものです。進化論自体は常に無神論者たちにとってお気に入りの学問であったことは言うまでもありません。
★十九世紀も終わりに近付いたころ、神の存在を否定する科学者たちは揃って進化が事実であると主張していたものです。しかし、彼らの中にさえも人間の起源が五万年もさかのぼると主張する者は一人もいませんでした。タイヤールは世界にピルトダウン人を紹介し、彼が十万年前に地上に存在したと主張したものです。進化論者たちはそれを聞いて喜びました。アーサー・キーツ卿は進化に関するその著作(1928年)に「これほどの進歩の証人であるわたしたちは幸運でした。このすばらしいピルトダウン人を手に入れたわたしたちは、以前考えられていたよりもはるかに古い時代から人類が存在していたことを知るに至りました」などと書いています。「種の起源」(1859年)を書いたチャールス・ダーウィンは懐疑論者たちに深い印象を与えたものです。ド・シャルダン自身もダーウィンの著作とその結論に対して、公の賛辞を惜しむことがありませんでした。
今日、まともな学者が一致している結論によれば、アダムとエバが存在したのは六千年ぐらい前のことになります。★1920年代の進化論者たちの傾向は人間の起源を可能な限り古いものにしようということでした。その一つの理由は、人種主義が一つの公然としたイデオロギーとしてある人々には熱狂的に受け容れられつつあった、ということがあります。彼らは、人間の起源が古ければ古いほど白人と黒人が同じ種に属さないことが証明しやすくなると信じていました。ですから、ある人種が劣等であると考えていたアドルフ・ヒットラーとかナチスにとってこのような傾向は歓迎されるべきものでした。
しかし、ヘイスティングスにある小さな家にたまたまド・シャルダンが住んでいて、運良く発見したピルトダウン人は、その他の批判者からも歓迎されたわけではありませんでした。他の分野の科学者たちはそれが本物であるという主張を補強することができませんでした。ヨーロッパで指導的立場にある科学者、特に歯科医たちはそれを「ナンセンス」として一蹴しました。彼らはあのあごが頭蓋骨にはまることが不可能であると主張していました。ピルトダウン人であれば歯が要るはずなのにこのあごは頭蓋骨から解剖学的にあまりにも違い過ぎるので、歯がそこに生えるのが不可能だったのです。
★訳者註・一応原文どおりに訳しましたが、これには異論のある向きもあるでしょう。ただし、人祖に原罪を犯すだけの責任能力があったのであれば、彼らにはそれに見合うだけの思考能力と現代ホモ・サピエンスと同等の大脳があったと推定できます。そうすればこの結論にも説得力があります。
深まる陰謀
大英博物館で働くある想像力豊かな館員が完全な、しかし想像上のピルトダウン人を、ちょうど漫画のスーパーマンを作るようにして、作成したのです。彼はちゃんと歯まで作成しましたが、まあ、何という歯であったことでしょう! 神の創造による地球上にあのようなものが存在したはずはありません。あれはいたずら好きな彫刻家による想像の産物でしかありません。
そのころ、タイヤールはヘイスティングスを去り、フランスに帰国していました。しかし、英国でも、ヨーロッパ全大陸でも新聞という新聞はこの大発見を報道し続けたので、一般人は非常に興味をそそられたものです。1913年の夏は季候も良く、何千人もの観光客がピルトダウンを訪れたのも当然のことでした。
発掘現場は不可解にも立入禁止になっていず、また警備員が常駐するわけでもありませんでした。だれでも勝手にのぞきまわり、堀り返し、土砂を移動することができました。それでも何かそれらしいものを発見した人は一人もいませんでした。
しかし、1913年8月30日、タイヤールがフランスから帰ってきたその日、何と彼はそこの砂利にしゃがんだ途端に一本の歯を発見したのです。それは大英博物館の人形の歯と全く同一のものでした。
この発見でタイヤールは科学者としての名声を確立しました。この一本の歯を発見するというような幸運は後にも先にも科学の世界では記録がありません。
賢明な読者はすでに推定されたことでしょうが、この歯は偽物であることが証明されました。その犬歯は現代チンパンジーのものであったのです。だれかがそれにやすりをかけ、染色し、大英博物館がでっち上げた歯と同じように見せかけたのです。★
今日、ピルトダウン「人」は人類学者たちからは大がかりな詐欺であったと広く認められています。ド・シャルダンは、たとえほかに協力者がいたとしても、この「大うそ」を意識的にでっち上げた詐欺師です。
★興味のある方はオックスフォード大学出版局が出版したThe Piltdown Forgery(ピルトダウンの詐欺)(1955年)をご覧下さい。
中国での発見 — ペキン原人
1923年、ド・シャルダンが初めて中国に行ったとき、彼はロックフェラー財団がペキン近郊で支援していた発掘に気づいていました。タイヤールはそんなところに人間が居住した痕跡があるとは思っていなかったにもかかわらず、何年か後に中国に帰るよう命じられた際には、完全に異なる意見の持ち主になっていたのです。
彼は第二回目の中国赴任に際して、まず三ヶ月間アビシニアでアンリ・ド・モンフリーと呼ばれる暴君と起居を共にしました。彼の伝記も発行されています。ド・モンフリーは船乗りで、犯罪者でしたが、おそらく奴隷売買にもかかわっていたでしょう。少なくとも彼が奴隷を所有していたことは記録に残っています。彼はタイヤールがお気に入りでしたが、彼が神父であることは信じようとしませんでした。ほかにも彼が司祭であることを信じてもらえなかった例は数多くあります。三ヶ月もの間ド・シャルダンはモンフリーのコーヒー園で彼と親しく暮らした後、中国本土に向かいました。
到着後間もなく、ペキン近郊の竜骨丘と呼ばれる場所で、タイヤールはペキン原人と言うよりも、むしろペキン原人たちを発見しました。数多くの骨格、頭蓋骨がそこらあたりに散らばっていたそうです。最初の発見は1929年12月1日でした。これが彼が成し遂げた二番目の「大発見」となります。
不幸なことに、読者もご承知かとは思いますが、これらの「大発見」は行方不明になってしまいました。そうです。消えてしまったのです。山のような骨、何トンもある骨、歯と骨が詰まったいくつもの大きな箱がなくなってしまったのです。タイヤールと共同研究者であったデイヴィッド・ブラック博士とウェン・チャン・ペイ博士は、自分たちの発見に関する研究論文を出版しました。しかし、その後十年ほどの期間に中国でその論文に接した人が何人かはいたのでしょうが、学会の興味を引くことはありませんでした。それでも最後には何人かの科学者がそれらの化石を調べる気になりました。ところが、ペキンには新発見の放射性炭素による年代測定法、従来のフローリンテスト、そのほかいかなるテストをしようにも、肝心の化石が存在しませんでした。これらの臨床的規範の使用によってペキン原人は決定的に偽物であると証明されるはずでした。しかし、信じがたいことにペキンで発見された化石は一つ残らず消え去っていたのです。では、なぜそんなことになったのでしょうか? ド・シャルダンによれば、それらの化石は貨物列車に積み込まれ、その貨物列車がどこに行ってしまったかだれも知らないのです。
タイヤールがそんなことを気にしたり、腹を立てたりしたでしょうか? とんでもない。その気配はありませんでした。彼の霊性によればあきらめてはならないはずでした。「あきらめてはいけない。この世的所有物に執着しないなんてとんでもない。諦観などは不要。自己主張は大事です。自分の権利は主張しなさい。この世には自分なりの貢献をするべきです」。これは彼の持論でした。それなのに、彼を間違いなく国際的知名人にしたはずのペキンでの発見が消失したとき、彼はそれを完全な諦観でもって受け止めたものです。彼はほとんど何もしていません。鉄道局への問い合わせさえもしていません。ただひたすら、自分の「発見」によって勝ち得た立場から自分の霊性を説き続けるだけでした。
パリのプール博士はタイヤールから新しい「失われていたリンク」を見に来るよう誘われていました。プール博士が見ることのできた残されていた唯一の証拠は、ばらばらになった猿の頭部の骨でしたが、頭蓋の部分は見せてもらえませんでした。彼が失望し、腹を立てたのは当然です。フランスに帰国した博士はL'Anthropologie(人類学)に記事を寄せ、ド・シャルダンの主張を退けました。
★レオ・S・シューマッハー師によるThe Truth about Teilhard (タイヤールに関する真実)には以下の文があります。「タイヤールの友人であり、師でもあったマルセラン・ブール博士がタイヤールの依頼に応じて中国にまで出向きましたが、プール博士はペキン原人が実は猿であり、ド・シャルダンの説が巧妙ではあっても、荒唐無稽であると宣言しています。ですから、合理的疑いの余地なくペキン原人はインチキでしかありません」。
ド・シャルダンの旅行
極東滞在中のタイヤールはチベット、東蒙古、ソマリランド、ハラス地方、イェーメンに旅しました。また、1931〜1932年には、シトローエン・クロワジエール・ジャヴネを駆ってアジア横断を果たしています。その後再びアジアを横断した後、シベリアを通ってフランスに帰国し、その足でロンドンと米国も訪問しています。
ド・シャルダンのAppearance of Man (人間の出現)にロベール・フランクールが書いた序文で、フランクールは上記の旅行について報告しています。またこれらの旅行の間にタイヤールが世界各地に小旅行をしたことを伝えています。1934年、タイヤールが中国南部に滞在したときなどは、マレー国境、ビルマ、ジャワにまで足を延ばしています。1935年にはインドを訪れていますし、1936年にもジャワを再訪、1937年にはフィラデルフィアはヴィラノーヴァ大学で講義しています。同年にはジャワを三度訪れたかと思うと、フランスと日本にも顔を出しています。タイヤールは第二次世界大戦中つまり1939〜1945年までは中国にとどまっていましたが、戦後ヨーロッパに帰っています。1951年と1953年にはアフリカに旅しています。1955年、タイヤールはニューヨークにいる友人のアパートに身を寄せていましたが、復活祭の朝急死しました。
六章 ド・シャルダンの勝利
それではここで、読者のタイヤール・ド・シャルダン理解を助けるために簡単に年代記を紹介しましょう。
1947年までに、彼は「神は崇拝の対象ではない」とか「アダムとかエバは存在したわけがなく、原罪なるものも存在しない」などと公に言って歩いていました。彼の行動は大胆そのものでした。年令も六十歳を超えており、宗教に対する彼の考え方も厚かましいものでした。ある友人に彼は「わたしには多くの友人がいるし、彼らの多くは戦略的地位に就いています。ですからわたしは将来のことを心配していません。わたしは勝負に勝ったのです」と書き送りました。まさにこの冷静極まりないド・シャルダンの言ったとおりでした。彼は神学校を堕落させたかったし、それに成功したのです。彼は近代主義と懐疑主義の種をどこにでもまき散らすことを望み、それに成功しています。
カール・ラーナーの登場
少なくともドイツ語圏の神学界で彼の後継者になったのは、その熱心な支持者で実存主義者であることを自認するイエズス会のカール・ラーナー神父でした。1939年も終わりに近付いたころから1942年に至るまで、ラーナーはオーストリアのウィーンとドイツで一騒動を起こしていました。ドイツの司教たちは彼の発言を非常に気にしていました。ザルツブルグの大司教は、ラーナーが伝播したあらゆる種類の非カトリック的概念で人々の魂が毒されるのを見て、ついに彼を非難しました。
教皇ピオ十二世自身も回勅『ミスティチ・コルポリス』を出されましたが、その目的はキリストの神秘体である教会中にまき散らされた誤謬を断罪することでした。明らかに、『ミスティチ・コルポリス』の目的は、カール・ラーナーとその誤謬を念頭に置いたものでした。この回勅がラーナーを抑え込むことを識者は期待したのですが、教会はそれほどの運に恵まれず、その直後の1947年、ラーナーはインスブルック大学で基礎神学の講座を受け持つことになりました。イエズス会はドイツ語圏の神学生たち、つまり将来の司祭たちの教育をカール・ラーナーの魔手に委ねたのでした。★
★ラーナーは自分の実存主義哲学に従って、客観的で不変の真理は存在しないと教えていました。彼の同僚とでも言うべきベルナルド・ヘーリング神父はこれを倫理神学の分野でさらに発展させました。彼によると道徳的掟は変化と疑いの段階にありました。彼にとって、ほとんどの事柄は「灰色」で、そのために正邪の区別は困難でした。
全ヨーロッパへの影響
ですから、「わたしには多くの友人がいるし、彼らの多くは戦略的地位についているので、わたしは将来のことを心配していません」とタイヤールが言ったことの意味が分かります。彼にはパリ大司教館内部に枢機卿以外にも友人がいました。そのほか、ベルギー、オランダ、スカンディナヴィアにも協力者が大勢いました。
第二次世界大戦後、近代主義的思考の不可避的諸結果がはっきり目に見えるようになりました。ヨーロッパ大陸の各地で信仰の劇的衰退が見られました。
a 米国で1950年頃 France Pagan (異教のフランス)という本が発売されましたが、読者はいわゆる「カトリックの国」の憂うべき霊的状態を知ってまゆをひそめたものです。
b そのころ、ヨーロッパを訪れたどれほど多くの観光客が帰国後、黒いヴェールを頭にかぶった老齢の婦人たちのほかにだれもいない、空っぽの教会について報告したことでしょう! カトリック信者としての習慣を民族の一世代が揃って放棄していたのです。
かつて実りの多かった畑はほとんど荒れ地になりました。ド・シャルダンとラーナーがどれほど成功したかのしるしです。
神の恩寵に恵まれて、米国のカトリック教会はそのころまでどうやら無傷で済みました。それでも中西部では少し「実験」がなされていました。震源地はミネソタ・セント・ポールです。男子パウロ会が常に「現代的アプローチ」とか「もっと時代に合った」カトリシズムの提示を探し求めていたのです。
1958年に全米横断旅行をする機会に恵まれたある司祭の友人が、あちこちで珍しい典礼を見たことを報告してくれたことを思い出します。しかし、米国のイエズス会は当時まだ健在でしたし、そのほかの修道会にしてもそうでした。
アメリカの転換点
1945年、アメリカの司教たちと修道会の長上たちは優秀な神学生を勉学の仕上げのためヨーロッパに送るという何ともすばらしい決定をしたものです。ヨーロッパ近代主義の危険を当時の司教たち全員が意識していたかどうかは神のみぞ知るです。しかし、教皇ピオ十世が回勅『ミスティチ・コルポリス』で、この陰険な異端が組織的に侵入していることを司教たちに警告していたのは事実です。ある神学生たちはローマに、またある神学生たちはルーヴァンで学びました。パリのカトリック大学で学んだ者たちもいます。しかし、そこは長年懐疑主義者とか無神論者のたまり場であった場所です。オーストリアのインスブルックで神学を仕上げに行った者を待ちかまえていたのは、ほかならぬカール・ラーナーでした。
後知恵にはなりますが、神学生の多くが正統信仰を失って帰国したのもそれほど驚くべきことではありません。世界で三万二千人もの司祭たちが還俗の選択をしたのも当然の結果です。シャルダン・ラーナー主義の産物であったこれら不運な司祭たちは、一般的におそらく自分たちが何をしているかも知らなかったのでしょう。懐疑主義、不確かさ、真理の相対主義は人生の意義、教会の必要性、秘跡の重要性などの基本的事実について、ほぼ不可逆的混乱をもたらしました。混乱した人たちが自分の混乱を人々に伝えたのです。優秀な若い人たちがヨーロッパで教化された挙げ句、重要なポストに就任するのです。多くは神学校教授、大学の学長、ある人たちは何と司教にまでなりました。
七章 恩寵の喪失
もし司祭、修道者としての召命を全うすることを望むのであれば、一つ絶対に必要なことがあります。それは祈ること、しばしば祈ることです。もし全く祈らないのであれば、それは召命の終わりと思って間違いありません。それは信徒のために執り行う典礼のことではなく、神との親しい個人的祈りのことです。また、感情的に高ぶらせることの多いエンカウンター・グループの祈りのことでもありません。そういう祈りはしばしば自己催眠術の一種でしかありません。
リゴリオの聖アルフォンソは、天国の聖人たちがそこにいるのは地上にいるときに祈ったからだし、地獄の霊魂がそこにいるのは地上で祈らなかったからだと説いています。祈りは救いをもたらします。祈りを怠れば救われません。司祭、修道者であるためにはこれを信じなければなりません。しかし、高校時代のタイヤールを教え、後にエチュード誌の編集長になったブレモン神父、ジョージ・タイレル神父、彼らの後継者の大群のせいで、霊性に関する急進的概念が導入され、その結果祈りの生活の必要性が軽視されるようになりました。
種々のニュアンスこそあれ、こういう概念はいわゆる単一行為と呼ばれる概念から派生したものです。単一行為なる概念はその昔十七世紀に教会から破門されています。それにはいくつかの形態がありますが、結局は「何かが起きてあなたが神のようになる」ということに尽きます。あなたと神が一つになれば、あなたの行為は神の行為であり、あなたは以前していたようなことをもういろいろする必要がなくなります。良心の究明も不要になります。御聖体拝領の準備も、感謝の祈りも必要ではありません。聖人に対する信心は無益。十字架とかキリストにだけ存在する神人両性の黙想も不必要です。何かが起きて、あなたの心をこのようなもろもろの義務から解放するというのが単一行為です。
ひとたび「わたしは自由である」と言えば、その自由を何に帰しても構わなくなります。あなたは「自分の考え方を新たにしなくては」とか「それが第二バチカン公会議なのだ」とか言うことができます。「第二バチカン公会議がそんなものをすべて廃止した」これは正に近代主義者たちの主張そのものです。
十七世紀に彼らはそれが神秘主義であると主張しました。その時も今もシナリオは同じです。司祭と修道者たちはこの新しい霊性を試して、教会に伝わる伝統的英知から解放されたと宣言します。最初は感情の高揚があったでしょう。しかしすぐに、彼らの精神的バランスにもよりますが、混乱に陥ってしまいました。そしてそれを「霊魂の暗夜」であるなどと間違って解釈したのです。このような現象が意味するのは、彼らが無責任な著者による無責任な霊的著作を読んだとか、近代主義がかった研究会に参加したとかいうことです。その結果、彼らは本物で健康な霊的生活に必要な伝統的霊操を放棄してしまいました。祈らなくなった彼らにとって、召命における堅忍の恩寵は途絶えてしまいました。
扱い困難な異端
この種の異端は始末に負えません。第二バチカン公会議中教皇パウロ六世は死に物狂いでこの異端と戦われました。ローマに忠実であった司教たちはその拡散するさまをほとんど手をこまねいて見守るほかありませんでした。なぜでしょうか? それは近代主義者が霊性とか霊的生活について話すとき、多くの教義を否定しているように見えないままに実は否定することができるからです。ですから、これらの現代的運動を断罪するとき、わたしたちは誠意と善意があって、キリストを愛している人たちを断罪しているような錯覚に陥るのです。
歴史は繰り返す
十七世紀にも、類似の異端を破門しなければならない立場にあった聖なる教皇がいました。彼は心の優しい教皇だったので、最後にはそうなさったのですが、それはためらいにためらって、涙を流してからのことでした。この教皇は福者教皇イノセント十一世のことです。彼は聖なる人で、真の紳士でしたが、「神学者」ではありませんでした。そう言えば神学者でなかった教皇は数多くいらっしゃいます。教皇イノセント十一世は神学の専門家が知っているほどには神学を知りませんでした。ですから、この教皇は静寂主義者の指導者ミゲル・デ・モリノスを聖なる人であると思いこんでいました。従って、多くの「神学者たち」の忠告を無視して、デ・モリノスの好き放題にさせ、誤謬が広まるに任せたのでした。教皇の処置は一時的に先送りさせられました。その理由は、デ・モリノスが静寂主義というサラダの大皿の中で、一つまみの正統的真理と山のような霊的用語に自分自身の誤謬を巧妙に混ぜていたからでした。
しかし最後にローマ教皇庁が静寂主義の異端を我慢できなくなり、また放置しておいてもそれが消えて無くならないと確信したので、彼らはこの聖なる教皇を魂の善のために断固として行動させることに成功したのです。1687年、教皇イノセント十一世は有名な「チェレスティス・パーテル」を発布して、静寂主義は公的に破門されました。もし、読者が当時のローマ事情を研究すれば、彼はまるで現今の事情が目の前に繰り広げられているような錯覚を覚えるでしょう。司祭たちは聖務日課を唱えようとしませんでした。修道女たちは司祭になりたがっていました。マッテオ・ペトルッチという名の司祭はこの「単一行為」の霊性を懸命に弁護する本を出版しました。彼は急進的であり、創意工夫に富み、率直でした。しかし異端者でした。それにもかかわらず、彼の友人たちは彼を枢機卿に任命するよう運動し、その運動は成功したのです。彼の司教区には女性司祭、女性助祭を含むありとあらゆる進歩的活動が見られました。彼の異端が名指しで破門されたとき、ペトルッチ枢機卿は最終的に自分の神学的、典礼的逸脱のすべてを検邪聖省で公に撤回しなければなりませんでした。
この種の異端は昔も今も初めは処理するのが極端に困難なように見えます。教皇ピオ十二世はこの異端のにおいを意識し始めました。そして教皇はこの奇妙な霊性に冒されていたドイツのイエズス会に好意を持ってはいましたが、断固とした行動をとらねばならないことを知っていました。もし読者が1950年から1958年の期間に出されたピオ十二世の司牧教書を読めば、この聖なる教皇が修道会指導者たちに警告をくり返し、彼らに伝統と正統信仰を守るよう父として勧めていることに気づくはずです。
ピオ十二世の意義深い行動の中には、1956年に行われた教皇イノセント十一世の列福式があります。言うまでもなくこれは静寂主義を破門に付した教皇です。
象徴的皮肉
第二バチカン公会議の会期中、公会議文書を作成したカトリック世界の司教たちは毎日聖ペトロ大聖堂に列を作って入場しました。入り口の片側には近代主義を断罪した教皇聖ピオ十世の墓があり、もう一方には静寂主義を断罪した福者イノセント十一世の墓があります。これら二人の聖なる教皇によって断罪された同じ誤謬が、これら二つの記念碑の間を通過した多くの公会議教父たちによって広められたのは、何という皮肉でしょう。
八章 一つの間違いが次の間違いを生む
もしタイヤール・ド・シャルダンの教えを一つの基礎的教義に煮詰めるとすれば、それはとどのつまり「アダムは存在しなかった」ということに尽きるのです。一見ささいなことのように見えるかもしれませんが、これは大事な点です。カトリックの教義によればアダムは人間の象徴などではなく、実在の人です。キリストはご自分を第二のアダムとさえ呼ばれました。実在のアダムを信じるか信じないかで、あなたの立場には天地の差が生じます。なぜかと言えば、アダムが存在しなければ、原罪も存在しないからです。
もし原罪が存在しなければ、わたしたちは原罪から救われる必要もなくなります。
もし救いの必要がなければ、カルワリオの丘で起こった出来事はいったい何だったのでしょうか? タイヤールはこれに答えることができません。しかし、彼はそれを犠牲とは呼びません。彼は決してカルワリオの犠牲について語ろうとしません。タイヤールはカルワリオでの意義ある行為については語りますが、ド・シャルダンのような人たちが言うすべての事柄と同じく「意義」とは不明瞭な言葉です。
近代主義者たちが確信しているのは、自分たちがカトリック教会の教えを信じていないということです。
彼らはキリストが新しいアダムであることを信じません。もし最初のアダムが存在しないのであれば、新しいアダムが存在するのは不可能になります。
もし原罪が存在しなければ、恩寵の喪失も、従って新たに恩寵の状態に戻される必要もなくなります。
ですから、ミサを彼らがどのように受け止めようとも、カルワリオでの犠牲がなかったらミサの犠牲も存在しません。
今日、典礼にはあらゆる種類のナンセンスが見られますが、その根本原因はこういうことにあります。
司祭の「意向」とは?
典礼の言葉がラテン語であろうと英語であろうとそれは問題ではありません。ある人たちは司祭がトレント公会議のミサを唱えても、教皇パウロ六世のミサを唱えても問題はないと言うかもしれません。司祭がその基本にある教義をカトリック的に理解し、信徒も教義をカトリック的に理解する限り、それほどの害はないと思ってもいいのでしょう。
しかし他方、わたしたちを罪から救うためにキリストがカルワリオの丘でご自分の生命を捧げられたことを司祭たちが否定しても、それほど害がなかったと思われています。
そうすれば、エキュメニズム、キリスト信者の一致、別れている兄弟などについて話し合っても無駄でしかありません。なぜかと言えば、別れている兄弟とはリヴァーサイド教会のロックフェラー一族とか、何も信じる者を持たない進歩的プロテスタントとかではないからです。別れているわたしたちの兄弟たちとは、ミサがカルワリオで起きたのと同じ犠牲であることを否定するあの「カトリック信徒たち」にほかなりません。
実際に、普遍教会は常にキリストがわたしたちの罪のために死んだとはっきり教えています。しかし、例えばハンス・キュング、カール・ラーナー、タイヤール・ド・シャルダンのような近代主義の著者を読めば同じことが書いてあるでしょうか? こういう人たちによって、ある人たちのミサへの信仰はすでに消滅しています。それに輪をかけてミサの国語化は、近代主義の司祭が「犠牲」の含蓄的意味合いに新しい意味合いを付加したり、割愛したり、さらには自分の気に入るように変形してしまうことを容易にしています。多くの教会で行われるこういうミサは本当にミサであるか疑わしいとさえ思います。
当然の結果として、この近代主義的不信は洗礼、品級の秘跡を含むそのほかの秘跡の必要性と執行にも同じく影響してきます。近代主義者の手に掛かった秘跡は有効なのでしょうか? それとも有効ではあっても疑いが残るのでしょうか? 洗礼を授ける司祭が原罪を信じていない、教会自体を信じていない場合を考えてみて下さい。★
★ハンス・キュングなどは、ある日「司祭がパンとぶどう酒に向かってこれはわたしの体、これはわたしの血であると唱えると何が起きるのですか?」と聞かれると、そっけなく「何も」と答えています。
倫理的派生効果
アダムがわたしたちの祖先であることを否定する結果、もう一つ重要な結果が生じます。もしアダムが存在せずに、従って原罪もないのであれば、原罪の諸結果もないはずです。ですから、近代主義者は、もろもろの情欲を伴うセックスと死は人類に対して神が元々計画していたと推論します。近代主義者にとって、性欲の無節制な傾きである情欲と死は堕落した人祖がもたらしたのではなく、人間にとっては自然な状態なのです。
1 セックス(と情欲) — カトリックの伝統的信仰は、秩序に従う傾向はあったとしても、不完全であった人間は原罪によってますます不完全になったと教えます。それ自体としてはよいものである性的本能は今無秩序になる傾向があります。堕落した人間には情欲がその一部として存在するようになります。ですから、救いの道にとどまるために、わたしたちは祈り、罪の機会を避け、聖母マリアの徳を見習い、自己抑制によって欲望の制御をしなければなりません。
死 — カトリックの信仰は、アダムが死ぬために創造されたのではなかったと教えます。死は人生の目的ではありません。人生の目的は救いです。死は罪の罰ですが、イエズスの功徳によって死は聖化されました。この真理はキリストが復活した意義の一部をなします。ド・シャルダンは死が「交わり」であると主張します。教会は死が罪の罰であると教えますが、タイヤールは罪の概念を黙想することを好まないので、死が罪の罰であることを認めようとしません。1941年、タイヤールは「わたしがそのために戦って生命をなげうってもいいと思う唯一の敵は静止です」と書いています。それは死とか道徳的悪とか物質的悪でさえもなく、静止が自分の敵であるというのです。
真理のドミノ倒し
タイヤールが主張するように、もしわたしたちがアダムとエバは神話であったと認めるならば、結論はわたしたちが経験する人間の具体的本性が、進化によって達成されるはずの自然的完成を除けば、そのあるべき姿そのものであるということになります。ですからあなたの本能には信頼してもよいことになります。犠牲とか抑制は無意味になります。四旬節の節制を守ることとか、金曜日に肉食をしないことには意味が無くなります。朝2時に起きて読書課を唱え、自由を放棄し、自己を否定し、人生の楽しみを断念し、汚く古い修道服を着るような中世期的修道会に入会するのは愚かなことになってしまいます。そういうことを自分がしないだけでなく、そういうことをする人たちを尊敬してはならないことになります。伝統的な修道者たちとか、修道会を創立した聖人たちを尊敬することももってのほかです。
現代はこんなことよりさらに進んでしまいました。正統カトリック神学の重鎮聖トマスに替わってカール・ラーナーが尊敬されるのが現代です。多くの司祭、修道士、その他の人々は、わたしたちが大事にしていた伝統的霊性を大声で非難します。彼らによると、あの昔の否定的人生観を捨てて、わたしたちは今「喜び」の時代に足を踏み入れるのだそうです。どのような「喜び」かと言えば、それは普通プレイボーイマガジンがもたらすようなセックスの喜び、淫乱の喜び、あらゆる種類の快楽主義の喜びにほかなりません。
このような考え方から、ある種の信じられないような結果をわたしたちは目にすることになりました。例えば、ある聖職者たちは同性愛を受容可能であると堂々と宣言するDignityなるグループの支持を表明します。彼らによると、そういうことも有効な本能、堕落した人間本性の自然な傾向であるそうです。
米国中西部にあるある匿名の神学校は、そこでの同性愛活動が目に余ったので閉鎖されねばなりませんでした。そうです。そこで起こったこういう問題の源はド・シャルダンのDivine Milieu(神的環境)の導入にほかなりません。若い神学生たちがこの書物を読み始めると、彼らの内的規律は瞬く間に消えてしまいました。タイヤールはどのような愛情であってもそれはよいものであると教えているからです。
ラーナー主義の魅力
カール・ラーナーは数多いその著書に「愛、愛、愛 — それが人生で出会う諸問題の解決」などと書いて人々を誘惑します。
★もちろんラーナーは正しくありません。キリストは「もしあなたたちがわたしを愛するならわたしの掟を守りなさい」と教えます。それが希望と信仰、自己否定と教会への従順、祈りとそれぞれの召命に伴う義務に組み合わせられた愛であれば、それは聖化と救いに役立ちます。
ラーナーには神と人が一つであり同一であるという狂った思想があります。これは教皇イノセント十一世が断罪した静寂主義の「単一行為」説をラーナーが焼き直したものです。彼はキリストの受肉によってわたしたち一人一人の人間の本性が神性と融合した、と説明しています。わたしたちが何と実体変化した、つまりほとんど位格的に神と一致しているというのです。ラーナー神父はこれがだれにでも起こっていると主張します。それが意味するのは、突き詰めると、わたしたちは具体的に悪を冒すことができないことになります。悪がなければ罪もないわけです。お分かりですか? これは非常にずるい論法です。しかし官能主義的な人物にとってこれは大歓迎でしょう。
★正しいカトリックの教えによれば、キリストだけが受肉した御言葉です。キリストにだけ神性と人性の二つの本性があり、人間には一つの本性しかありません。その魂は恩寵を注入されて、救いにつながる業を行うことができるようになります。それにもかかわらず、個々の善行は恩寵との協力と道徳的善に向かい、道徳的悪を避ける彼の意志が意識的に行為することを必要とします。
ラーナーによれば、あなたが人間とかかわるときに、いやおうなくあなたは神とかかわるのです。あなたが「人」と言うときにあなたは「神」と言っているのです。ですから以下が言えます。
a 御聖体を礼拝する必要はありません。神はあなたの中に内在します。
b もしあなたがだれかに好意を持っていると感じたら、あなたは彼もしくは彼女を愛して、性的関係による「意義深い」かつ神的関係を持ってもよろしい。
c あなたの住まいが裕福な郊外にあり、貧しい人たちが遠く離れていたとしても、貧しい人への愛も含めて、どのような意味であってもあなたが欲するままにだれでも愛しなさい。そうすればあなたは神を愛していることになります。
d 人格でありなさい。つまり、本能的欲求と傾向に身を任せなさい。伝統的な教会の掟とか規則を気にすることはありません。
ざっとこんなものです。この「新」神学は混乱の源であり、あいまいで、(部分的には)幾分かの真理を利用しています。それは不条理であり、それ故におそらく悪魔に由来します。
それなのに、人々はそれを何とたやすく受け容れることでしょう!
それはなぜでしょうか? なぜなら、それは人間の弱さ、官能、傲慢、怠惰に訴えるからです。しかも同時にそれは「新しい」霊性の衣をまとっています。この複合体はなかなか手強いのです。
第九章 流れは変わらねばならない
1981年の時点で、わたしたちの教皇は着任からまだ間がありません。教皇には強い神学的背景があります。これはこれから述べるように二つの意味で意義深いことです。
まず、この近代主義が着々と足場を固めつつあったとき、教会指導層のかなりの部分は眠っていました。その巧妙さを認識するのがたやすいことでなかったことは認めます。それだけではなく、この新神学と変化へのこの熱望の後ろに悪意の意図が潜んでいるなどとだれが疑ったことでしょうか?
しかし、教皇ピオ十二世は繰り返し繰り返し司教たちと修道会総長たちに書簡を書き、にべもなく、明瞭この上なく彼らに警告しなかったでしょうか? これらの「新しい」思想が広がらないように気を付けて下さい。特に以下の考えには気を付けなければなりません。
1 わたしたちはアダムの子孫ではない。
2 アダムとエバの話は神話である。
3 原罪は存在しない。
教皇ピオ十二世はすべての修道会総長に、以上のようなことを講演とか、書物とか、その他の方法で拡散させないように警告なさっています。しかし、教皇によるこの命令は大方無視されてしまいました。そして、今日わたしたちはその恐ろしい結果を目の当たりに見ているのです。
今日、わたしたちは摂理的にヨハネ・パウロ二世を教皇にいただく恵みを受けています。聖霊の極めがたい導きで、キリストの代理者ヨハネ・パウロ二世が現在教皇であることを著者は感謝しますが、感謝する理由はほかにもあります。
1 前述しましたが、何事が起きつつあるかしっかと把握していた一人の人がいました。トミズム研究センター、ローマのアンジェリクムで教えていたレジナルド・ガリグー・ラグランジュ神父がその人です。ガリグー・ラグランジュ神父は忠実で熱心な神父としての評判だけでなく、教義神学の優れた教授としても知られていました。彼が指導した学生の中に一人特別な学生がいました。彼は毎日のようにこの学生と顔を合わせ、十字架の聖ヨハネの神秘神学に関する彼の博士論文の指導をしたものです。この学生の名はカロル・ヴィイティワでした。
ド・シャルダンの誤謬を見張り続けたこの番犬、正統信仰の誠実な旗手の弟子であった学生が、現在聖ペトロの座に着いている教皇ヨハネ・パウロ二世であることを喜びます。
2 新しい教皇が発した公的勅令の一つが回勅『レデンプトール・オミニス』です。それは、それまでの二十九年間でアダムが現実に存在したと主張する最初の回勅です。この回勅はアダムと原罪の諸結果について力強く教えています。★
★1968年6月30日、教皇パウロ六世も回勅ではないものの『神の民のクレド』を出し、トレント公会議の教えにさかのぼって、教皇の権威をもってアダムと原罪について強力に教えておられます。
創世記の強調
ヨハネ・パウロ二世は教皇位に就かれて以来、しばしば創世記とアダムについて話しておられます。毎週のオッセルヴァトーレ・ロマノには例えば「わたしは教皇位に就いたばかりです。ですからアダムとエバの始めに戻って黙想しましょう」という具合に、よくこういう事柄を取り上げて話されます。
これは偶然などというものではありません。カロル・ヴォイティワはガリグー・ラグランジュ神父の膝下で学んだ優秀で、正統派の神学者だからです。
教皇と神学者
何年かの期間、教皇は外交畑の出身者が続きました。教皇パウロ六世の後で、枢機卿たちは「神学者」の教皇を求めていました。ヨハネ・パウロ一世になられたルチアノ枢機卿は神学者、しかもオッタヴィアーニ枢機卿の弟子であった保守的神学者でした。カトリックの世界は、進歩主義者たちは当然例外としても、彼が教皇に選出されたことを喜んでいました。そして、その突然死には同じくショックを受けたものです。
後継者である現在の教皇は伝統的で反共産主義的なポーランド教会、かつ深い神学研究という背景から選出されました。将来が明るいことを希望しましょう。
誤って提示された第二バチカン公会議
先ほど、著者は回勅『レデンプトール・オミニス』に触れました。この回勅には第二バチカン公会議文書、そして『現代世界憲章』からの引用さえも多くあることを付け加えます。近代主義者たちが幅を利かし、公会議に影響を及ぼしてはいますが、★正統信仰と第二バチカン公会議の間に矛盾はありません。問題は公会議文書が恐ろしく元気のよい進歩主義者たちによって解釈を受けていることです。彼らの名前を挙げるといずれもイエズス会のエイヴリー・ダレス神父、R・A・F・マッケンジー神父、C・J・マックナスピー神父、ドナルド・カンピオン神父、ジョン・コートニー・マレー神父、その他です(ニューヨーク、アメリカ・プレス、イエズス会のウォルター・M・アボット神父編集長、The Documents of Vatican II, With Notes and Comments 参照)。その結果、米国を始めとする英語圏の国で人々は異様な註、異様な解釈付きの公会議文書を読むことになり、米国司教の大方は主に左翼がかった「解釈者」に従うことになります。
例えば、カンピオン神父が『現代世界憲章』の本文への自分自身の註で「他の箇所と同じくここでも、タイヤール・ド・シャルダンのような思想家たちがDivine Milieu で発展させた洞察との両立を認識するのは容易です。憲章の主張は1940年代の新神学に見られる基本的霊感を批准しています」と書いています。この種の注釈は多くの人たちが機会あるごとに繰り返しており、さらに多くの機会に講演会とか研修会、書物、雑誌の記事などで主張されました。
★ただ、『信教の自由憲章』だけは理解困難で、大方のカトリック信者には余りにもあいまいに見えます。
新神学の諸結果(近代主義・進歩主義のための婉曲語法)
ド・シャルダン、彼の先輩たち、彼の弟子たちのために神学校も修道院も空になり、道徳は広く退廃し、ミサ聖祭とカトリック信仰の実践は質量共に考えられないほど急速に衰微しています。
希望の時
しかし、教皇ヨハネ・パウロ二世は神学者です。彼のためにわたしたちは毎日祈っています。教皇は第二バチカン公会議の文字にも霊にも忠実にとどまるだけでなく、創世記の文字にも霊にも、また教導職にもすべての側面に心から忠実にとどまるはずです。
教皇ヨハネ・パウロ二世はいわば叩き上げです。彼は三十八歳でポーランド・クラカオ司教になり、四十二歳で枢機卿の位に挙げられました。教皇はその当時から学識、聖性、神の母に対する熱心な信心で知られており、枢機卿団の中ではだれよりも強く回勅『フマネ・ヴィテ』を擁護したものです。教皇パウロ六世はこれを認め、彼に祝福を送りました。
イエズス・キリストの教会が伝えるべき公的教えは有能な教皇によって守られているように見えます。
「イエス・キリストは、きのうも、きょうも、いつまでも変ることがない」
(聖パウロのヘブライ人への手紙十三・八)
エピローグ Ⅰ
ド・シャルダンと近代主義の最終決定
1 ガラバンダルとかサンダミアノとかベイサイドで、聖母の出現があったなどと聞くと、大体の場合、教会の認可はまだないのではないか、などと言う人が必ずいるものです。それなのに、多くの現代カトリック信者は、教会から六度も断罪されているタイヤールのメッセージであればためらうことなく受け容れるのです。それだけではありません。彼の哲学はカテキズムに組み込まれて、感受性の強い若い人たちの良心を形成するのです。
2 タイヤールは自然と超自然、創造主と被造物、物質と霊魂の垣根を取り払いました。このような概念を哲学では一元論の誤謬と言います。
3 現代の進歩主義者たちはタイヤールを聖トマスと比較したがります。しかしそれはちょっとした丘をエベレストと比較するようなことに相当します。
4 ド・シャルダンは教会権威筋からの断罪と警告に心から従うことを拒否しました。しかし口先だけで従うように見せかけはしました。これはまるで教師から叱られて外面的には従っているように見えても、心の中では確信的反逆者であり続ける子供のようなものです。タイヤールは長上に大声で反論こそしませんでしたが、彼らに禁じられたこれら誤謬に満ちた危険な主張を説き、書き続けました。講演とか謄写印刷のパンフで彼は教会に禁止された主張を広め続けました。タイヤールはローマが彼に署名することを命じた信条にことごとく署名しています。しかし、彼はE・ル・ロワに「自分の主張または使命感をいささかも変更していない」と書き送っています。
5 ペキン市内と近郊に滞在していたころ、彼はしばしばかの地の上流社会が催す晩餐会に招待されました。ペキンにはかなりの数になる白ロシア人、ヨーロッパとアメリカの実業家、富裕な家庭の子弟たちが住んでおり、彼らは貧しい中国人たち相手の商売で大儲けしていたものです。その間、ド・シャルダンが司祭らしい仕事をした証拠はほとんどありません。
6 近代主義者たちはそれが神法であっても教会法であっても、掟が好きではありません。そこから彼らは掟を勧告に格下げしようと熱心に主張します。例えば、ミサが今日的でなかったり、意義深くなかったりするのであれば、出席しないでもいいと教える修道女は珍しくありません。彼らはイエズスを救い主としてでなく、教師として理解したがります。彼らは説教壇で話すのは好きですが、告解室で罪の許しを受けるのは嫌いです。彼らは聖体拝領は好きでも、ミサが犠牲であることを認めたがりません。時として彼らが聖体降福式を執り行うことはありますが、それは自分たちの個人的確信からではなく、寄付をよくしてくれる信者たちの機嫌を取り結ぶためです。
7 近代主義者たちは伝統的な祈りが嫌いです。彼らの注意集中力は短く、普通あれこれと新しいものを導入したがります。また、普通、彼らは非常に世間的です。彼らの服装にしても、休暇にしても、髪型とか持ち物にしても世間の人たちとさほど変わりません。もう一つの特徴は、貧しい人たちとか少数民族に対する愛についてはしばしば熱心に語るのです。ですから進歩主義者たちはカルカッタのマザー・テレサと写真に写りたがります。
エピローグ Ⅱ
タイヤール・ド・シャルダン自身とその著作に関する教会の決定
1926年 — ド・シャルダン神父のイエズス会長上が教職に就くことを彼に禁止。
1933年 — ローマがパリでの教授職を退くことを命令。
1939年 — ローマが彼の著作L'Energie humaine を断罪。
1941年 — ド・シャルダン最重要著作 Le Phenomene humaine をローマに提出。
1947年 — ローマが彼に哲学の問題について書いたり教えたりすることを禁止。
1948年 — ド・シャルダンイエズス会総長からローマに召喚。総長は彼の最重要著作 Le Phenomene humain が聖座から出版許可されることを希望していたが、1944年の禁止は更新される。ド・シャルダンはコレージュ・ド・パリで教えることも禁止される。
1949年 — Le Groupe zoologique の出版許可願いが却下される。
1955年 — 修道会長上たちはド・シャルダンの国際古生物学会出席を禁止。突然死去。
1957年 — 11月15日、聖座の最高権威がド・シャルダンの著作を教会施設の図書室に置くことを禁止。彼の著書はカトリック書店でも販売禁止。外国語への翻訳も禁止。
1958年 — 4月、イエズス会スペイン管区がすべてのイエズス会刊行物で、事前に教会の検閲を受けることなく、聖座に挑戦してド・シャルダンの著作集刊行に踏み切ったことを通知。
1962年 — 6月30日、ローマ聖座からの警告「死後出版の著書も含めた何冊かのタイ ヤール・ド・シャルダン神父の著作が編集・出版され、広く頒布されている。実証科学のかかわるいくつかの点に関する判断から引き離して考えると、前述の著作はあいまい、かつとんでもない間違いであり、裁治権者と修道会長上、神学校校長、大学総長たちに、タイヤール・ド・シャルダン神父と彼の弟子たちの著作に含まれる誤謬から、特に若い人たちの魂を守るように警告する」。
1963年 — ローマ代牧区は9月30日、ローマのカトリック書店がド・シャルダンの著 作とそれらを支持する著作物を返品することを命じた。この文書は10月2日de Chretiene (sic)に再掲されている。
1967年 — (1967年10月20日、ワシントンにあるバチカン使節団がタイヤールの著 作に関する警告が撤回されたかどうかの質問に対して回答。)「タイヤール・ド・シャルダン神父の著作に関して教理聖省が発した警告は現在も有効であることを通知します。彼のどの著書に関しても区別はなされていません。1962年6月30日に出された警告の英語訳を同封します」。
補遺 A タイヤールの引用
人種問題に関して
1 人種の不平等 — 「世界を旅すればするほど、人々はこれほどの生物学的証拠を無視してまで人種の平等を認めるという大きな間違いをしていると感じます」。
2 中国人 — 「中国人は進化が止まってしまった原始人であり、わたしたち白人と比較して、人類学的には劣等な本質を備えた未進化の犠牲者である可能性について…ますます確信を持つようになりました」。
3 黒人 — 「組織された社会にとって人間的にいくらそう希望していても、わたしたちは人間の層が同質でないかもしれないことを忘れてはなりません。そうでなければ、中国人にも黒人にも、生物学的不可能性によって白人とは異なる、特別な役割を見つけてやらなければならないでしょう」(1927年4月6日)。
4 アフリカ — 「土着民たちは増加したり、絶滅したりするでしょう。人はわたしが残酷であるとか、カトリック的でないとか言うかもしれません。しかし、真実はと言えば、進歩とは、与えられた時代を生き延びてしまった者たちがすべて滅びるように働きかけるものなのです」。
5 インド — 「ヒンズー教徒たちはわたしをがっかりさせました。彼らを見ていると進化の力が余り働いていないようです」。「インドは中国やマレー同様自治能力はないようです」。
政治問題について
1 「ファシズムは未来にその腕を広げています…もしかすると、ファシズムは明日の世界の設計図なのかもしれません」。
2 「左翼の進歩主義者と布教学者たちに対して、わたしはムッソリーニと共に立ち上がります」。
3 「平和とは征服のより進んだ過程でしかありません」。
4 「個人的に、わたしはファシズムが反進歩主義的勢力をかばったりしなければ、その苛酷なやり方を許したくなります」。
5 「進歩的民主主義者は基本的には本当に進歩的独裁者と変わりません」。
新宗教創立について
1 「創造、霊感、奇跡、原罪、復活、その他の共通理解に関して精神を従わせなければならないあの移行について考えるとき、わたしは時として少し怖くなります」(1922年12月17日の書簡)。
2 「ローマはわたしが教職にあることを望みません。しかし彼らがわたしを嫌っているとはとても思えません。しかし、彼らは宗教を救うことを考えているのです…わたしはすべての人的つながりを絶つことに大きな喜びを感じます」(1927年2月14日の書簡)。
3 「わたしの興味をますますかき立てるのは、自分自身の中に、そしてわたしの周りに、新しい宗教を確立すために努力することです。(もしよろしければ、それを改良したキリスト教とでも呼びましょうか?)その人格的神はもう過去にいた新石器時代の領主的存在ではなく、世界の偉大な魂なのです…」(1936年1月26日、レオンティーヌ・ザンタに宛てた書簡)。
4 「わたし自身の原則に従えば、わたしはキリスト教と戦うことができません。わたしはそれを変形させ、改宗されるために中からだけ働きかけることができます。革命家的態度の方がもっと容易で、楽しいかもしれません。しかしそれは自殺的というものです。ですからわたしは一歩一歩、粘り強く進まねばなりません」(1941年3月21日の書簡)。
5 「わたしには戦略的位置にいる多くの友人がいます。ですから将来に関して安心しています」(1947年9月24日の書簡)。
6 「キリストは救い主です。しかし、キリストも進化によって救われたことを付け加えなければなりません」( Le Critique、1955年)。
マルキシズムに関して
1 1948年、タイヤールは Trois choses que je vois(わたしに見える三つのこと)を書き、その中で、キリスト教の人間的暖かさと「マルキシズムの合理的力」とが結ばれた真に人間的信仰の採用を提案しています。(★人間的暖かさ、つまり愛、愛、愛が現代進歩主義陣営からどれほどしばしば聞こえてくることでしょう!)。
2 米国カトリック教会の停滞を考察したタイヤールは、ある友人に書いた手紙に「マルキシズムを思い切って取り入れたらまた活発になるでしょう」と書き送っています。
補遺 B ド・シャルダンの教えに関する識者のコメント
1ジャック・マリタン(幾分か近代主義思想にかぶれていたフランスの哲学者)
a 彼は、タイヤールが「聖トマス・アクイナスについて全く無知であったか、忘却してしまったのであろう」と批判します。
b 「タイヤール自身の中で本質的にもっとも問題は個人的体験です。まことにこの体験は彼がそれを分かち合う手段を探す努力をしたものの、決して伝わってきませんでした。しかし創立者によってでっち上げられ、マスコミが伝播したイデオロギーであるタイヤーディズムは一つの教義として提示されます」。
c 彼はタイヤールの弟子たちが人々を混乱させるだけでなく、もしそれを真剣に受け止めようものなら、キリストを救い主でなく、進化者に変身させてしまう、と批判します。
d 「熱心なタイヤール主義者から、キリスト教と彼の理論を両立させるのが不可能であると思う人はだれでもまだ彼を理解していない、などと聞かされるともういやになります。それだけではありません。キリスト教教義の方がタイヤールが持っている進化の概念に歩み寄るべきであると連中は主張するのです」。「進化は何も説明しません。説明され、証明されねばならないのは進化の方です」。
2 ペトロ・アルペ神父(1965年以来イエズス会総長、元イエズス会日本管区長)
「タイヤールは哲学者でも神学者でもありませんでした…悪い、間違った、あいまいな概念しかありませんでした。彼は目立たず、一貫性が無く、未熟で、自分の思想を明瞭に表現することができませんでした」。
3 ポール・ハレット
「タイヤールがあたかも、その世界観が普遍化することを運命づけられた教会教父であるかのように彼を引用する人たちは彼が実際何を言っているかをしっかと調べてみればいいのです。そうすればタイヤーディズムがスピノザの汎神論に新しい衣を着せたようなものであることに気づくでしょう。それは感傷的無神論に過ぎません」。
4 トマス・モルナー
a タイヤールは徐々にしかし確実にキリスト教から世界礼拝教に移行しつつありました。(タイヤール自身の言葉を借りると、「わたしがキリストに求めるのはわたしが礼拝することのできる力に彼がなることです。キリストに願うのはわたしが礼拝することのできる宇宙になることです」)。
b 「…自分の主観的な直感を教会が教える教義に置き換えた不安定な思想家」。
5 ディートリッヒ・フォン・ヒルデブランド
この高名な哲学者はド・シャルダンを表面的で、恐ろしく混乱している思想家、その教えは決してカトリック思想と両立できない、偽りの預言者であると位置づけました(フォン・ヒルデブランド著「偽りの預言者 タイヤール・ド・シャルダン」)。
6 レオ・S・シューマッヘル師
1979年5月19日発行のTwin Circle 誌で彼は読者に「タイヤールは聖人か? 異端者か?」と問いかけました。結論は「数多くの人が彼を賞賛していても、彼は新しい宗教を創立することを意図して、カトリックの教義を自分の目的にかなうように改造しようとしていました…それで彼は新しい信仰を作り出し、その新しい宗教をカトリックの用語を使用してカトリックの信仰と見せかけていました。彼が使用する言葉は確かにカトリックのものではありますが、意味はしばしば違います。それで多くの人たちはだまされて、彼が何を目論んでいるかを明瞭に述べている箇所さえも間違えて解釈し続けるのです」。
7 アンリ・ランボー(The Strange Faith of Teilhard de Chardin の著者)
「二つのことが言えます。その一つは笑わせるということです。最良の冗談は短い冗談であるとは言いますが、タイヤールを従順の模範として世に紹介するなどとんでもないことです。彼は正にその反対でした。表面的には従順を装ってはいましたが、最後まで帰順を拒む革命家でした。ローマは彼に何度も繰り返して彼が間違っていることを告げますが、彼は自分の頭にある宇宙をいささかも変更しようとしませんでした。彼は一発で全思考を変えるように命じられたわけではありません。そのようなことは簡単ではありません。しかし、彼は少しなりとも努力したり、反省したり、ローマが彼に言っていたことと自分の世界観、もしくは自分が世界観であると思いこんでいたもの、を両立させる方法を探すことができたはずです。しかし、そのような努力は皆無でした…彼には教会の命の言葉を受け容れる用意が全くありませんでした。それどころか彼の方が教会に命の言葉を教えようとしていたのです。彼の大きな夢は自分が教会の助産婦になって、年老いた母親が胎内に無意識に抱えている新しい信仰を産み落とさせることでした。その新しい信仰が全人類にとって未来の宗教になるはずでした」。
8 フィリップ・トロワー(The Church Learned and the Revolt of the Scholars の著者)
「…(タイヤールは)権力と策謀を礼賛しました。ムッソリーニのアビシニア侵攻を文明の勝利とさえ見なしました。ヒットラーとムッソリーニが勝ち誇っている限り、彼らに対する賞賛の言葉を惜しまなかったものです…共産主義も彼の称賛の的になり始めました。一般的に彼はアフリカ人を軽蔑していました」。
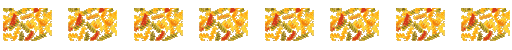
訳者後記
タイヤール・ド・シャルダンについては、「カトリック生活」97年3月号「キリストを生き、愛した人たち」のコーナーで「彼は生前望んでいたように復活祭の日に生涯を終え帰天されました」と、まるで聖人のような扱いです。ラベルはカトリックであっても中身には混ざりものがあります。こういうカトリック出版物が増えていますから気を付けましょう。教皇庁の新聞であるはずのオッセルヴァトーレ・ロマノ英語版1999年10月20日号5ページにさえ、歴史に残る種々のキリスト像の一つとして、ポーランドのアルフォンス・ノッソル司教が、ド・シャルダン思想の宇宙的キリストについて触れているのが引用されています。読者はお分かりのように彼は無視されてしかるべきです。
日本にはタイヤール・ド・シャルダン研究学会なるものがあって、著名なカトリック神父たちが名を連ねています。これらの神父に関して読者に警告する意味で全員の名前を公表したかったのですが、思いとどまりました。必要な方には連絡があれば教えます。1959〜1963年、東京四谷の神学校にいたわたしはイエズス会のフリッシュ神父からタイヤール・ド・シャルダンへの畏敬の念を教え込まれました。何しろこちらは一介の無知な神学生で相手は知的巨人にさえ見えた教授です。ド・シャルダンの思想を理解できないのは自分の頭が悪いせいであろうと思って、いわば括弧に入れたような状態で長年過ごしてきましたが、ポール・ウィッケンス神父の「否定されたキリスト」を読んで、理解できなかったことの方が正解であったと分かりました。そう言えば頭脳明晰でド・シャルダンを理解、支持していた多くの神父たちの中には還俗した人たちがかなりいます。本書のようにタイヤール・ド・シャルダンを真っ正面から批判した本は日本のカトリック出版界に見られません。もっと大部の類書は外国に多数あることも今回初めて気づきました。タイヤール・ド・シャルダン批判の入門書として本書が多くの人に読まれることを希望します。
なお、日本におけるシャルダン学会のリストを入手しました。残念なことに、多数の聖職者の前が見られます。近い中に本欄で発表しますのでご期待下さい。
成相明人
To the ![]() of this file
of this file